|
接峰面・接谷面
標高メッシュ、あるいは標高メッシュが登録されているプロジェクトで、各種の地形解析を行い、新たに標高メッシュを作成します。
- ベクターメニュー:[ツール]-[標高メッシュ]-[段彩陰影図]-[接峰面・接谷面]
- 標高メッシュメニュー:[標高]-[効果]-[接峰面・接谷面]
- ■ 操作方法
-
- ここでは標高メッシュデータをベクタープロジェクトに登録した状態で、処理を行ないます。
プロジェクトファイルを開きます。
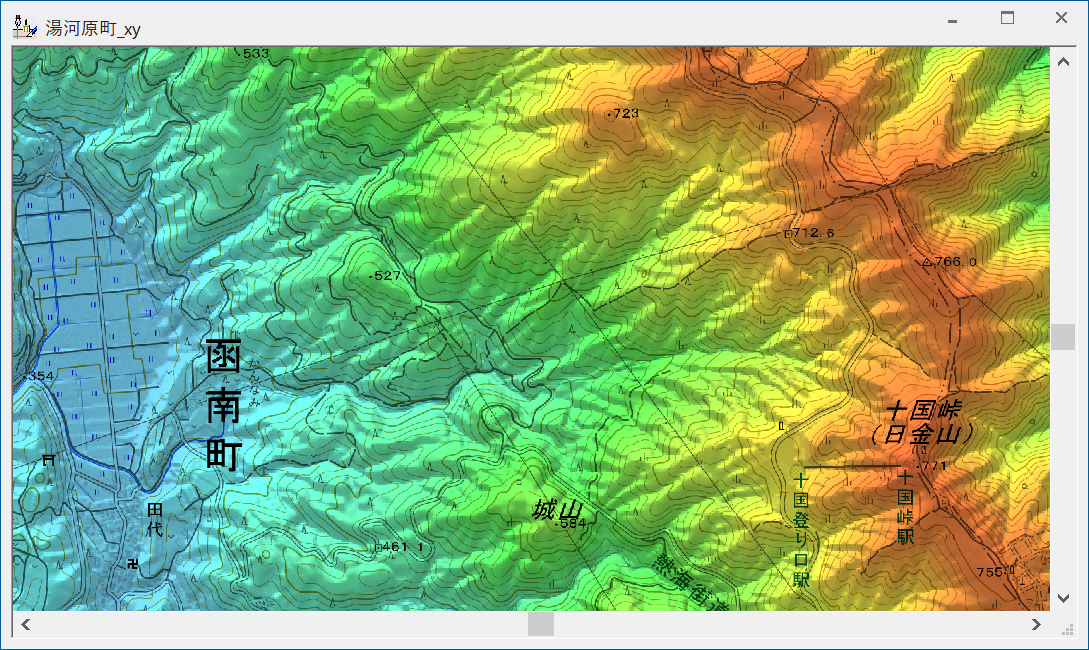
- [ツール]-[標高メッシュ]-[段彩陰影図]-[接峰面・接谷面]を選択します。
- [接峰面・接谷面メッシュの作成]ダイアログボックスが表示されますので、処理する項目にチェックをします。
同じパラメータで良ければ、複数の処理を一度に行なう事ができます。
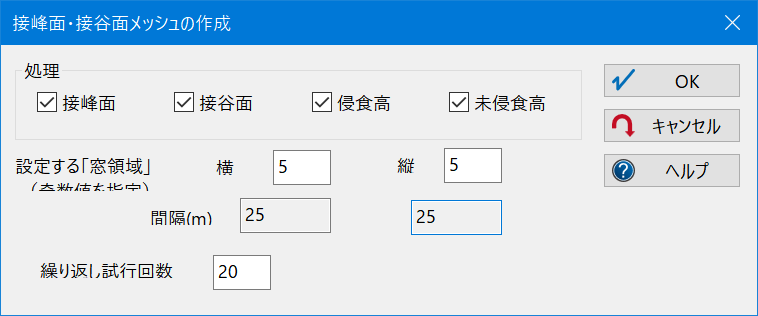
- [処理]
- 地形解析の手法を選択します。一度に複数の処理を実行する事も可能です。
- 接峰面(せっぽうめん):山頂部や尾根部は浸食を免れた原地形の一部と考え、山頂部に接するような仮想面をいいます。
- 接谷面(せっこくめん):接峰面とは逆に,谷底に接する仮想の面をいいます。
- 侵食高:作成された接峰面の標高から、元の標高メッシュの標高を差し引いて作成されます。
- 未侵食高:元の標高メッシュの標高から、接谷面の標高を差し引いて作成されます。
- 設定する「窓領域」
- 標高メッシュに対して、指定した窓領域(ピクセル)を当てはめ、地形の最高点の情報から再度標高メッシュを作成します。
すぐ下には、入力した窓領域に相当する間隔(m)が表示されますので、設定値の目安となります。
※通常は、5×5を設定します。
- 繰り返し試行回数
- 滑らかな地形にするため、処理を繰り返す回数を設定します。
※通常は、10〜50を目安に設定します。
▼ 接峰面(「繰り返し試行回数=10」)
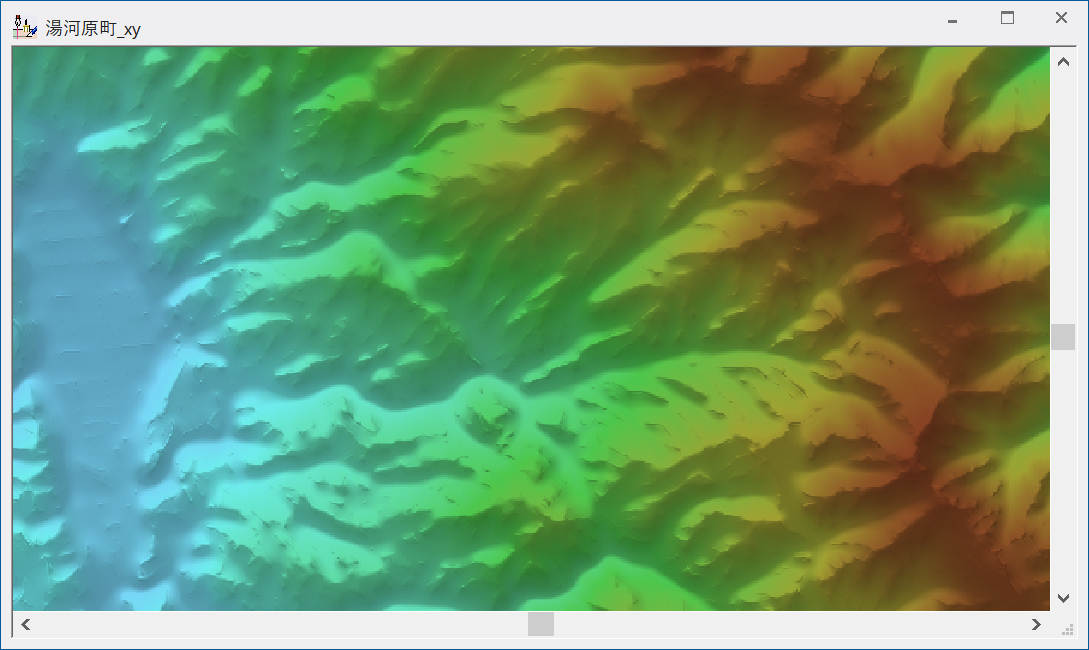 |
▼ 接谷面(「繰り返し試行回数=50」)
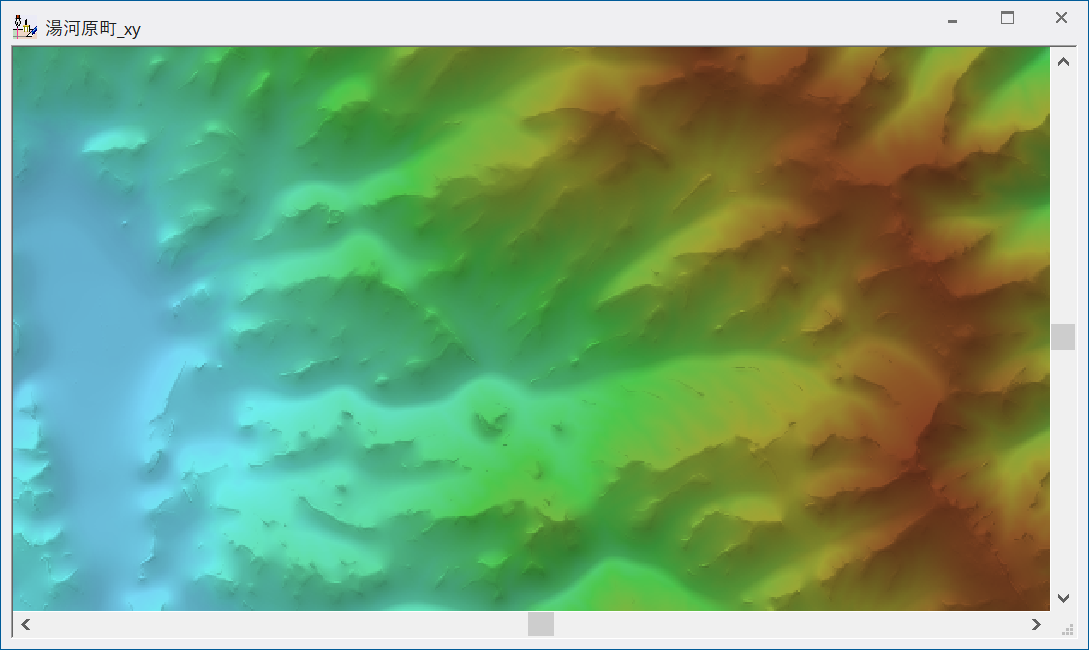 |
例えば、
- "接峰面"において、窓領域を5×5、繰り返し試行回数を20に設定した場合、その中(計25ピクセル)での平均値を求めつつ、その値が元の標高よりも高い場合だけ置き換えるといった処理を20回繰り返します。
- "接谷面"では、接峰面と逆の処理となり、元の標高よりも低い場合だけ置き換えるといった処理を行います。
- <OK>ボタンを押して、処理を実行すると、作成された標高メッシュが表示されます。
|
















