|
【ネットワーク解析】最短到達領域解析(ネットワーク領域分割)
このメニューを実行すると、ポイント(基地)を終点として、ネットワークを介して最短で到達できる領域をポリゴン化します。
ネットワークの解析はノード単位で行われ、結果の領域をポリゴンにして作成します。
ポリゴンにはポイント(基地)の属性が転記され、また、ネットワークのノードには、最寄のポイントまでの距離が転記されます。
- ■ 設定方法
-
- 以下のようなポイントがあるプロジェクト上で、[ツール]-[ネットワーク解析]-[ネットワーク最短到達領域解析(ネットワーク領域分割)]を実行します。
アクティブレイヤーに基地となるポイントがない場合は、このメニューは実行できません。
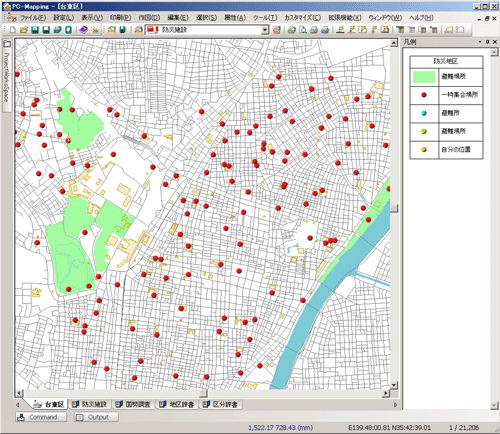
- メニューを実行すると、[ネットワーク最短到達領域解析(ネットワーク領域分割)]ダイアログボックスが表示されます。
ネットワークの解析はノード単位で行われるため、長いアークがある場合は、精度を向上させるため、[一時的に、指定値より長いアークを分割してから処理する]オプションを使用して下さい。
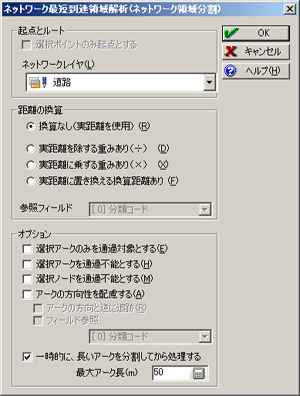
- 設定を行い、<OK>ボタンを押すと、以下のような結果となります。
例えば、このサンプルプロジェクトでは、「自宅」ポイントから道路ネットワークを介した最寄の集合場所(赤いポイント)は、「A」ではなく「B」という事になります。
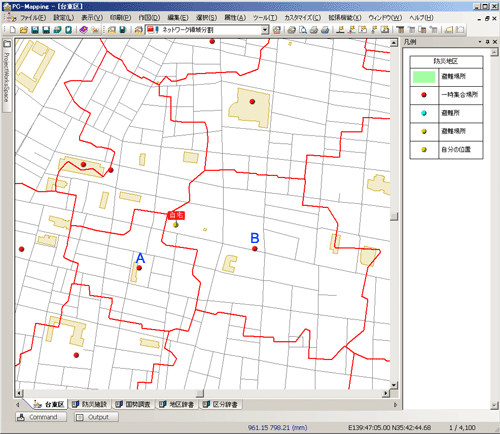
同じプロジェクトで[ツール]-[空間統計解析]-[ボロノイ分割図生成]を実行した場合(=道路ネットワークを介さない場合)は、以下のようになります。
単純に点間の距離では「自宅」から近い集合場所は「A」ですが、実際に道路を通る事を想定すると、「B」の方が近い事が分かります。
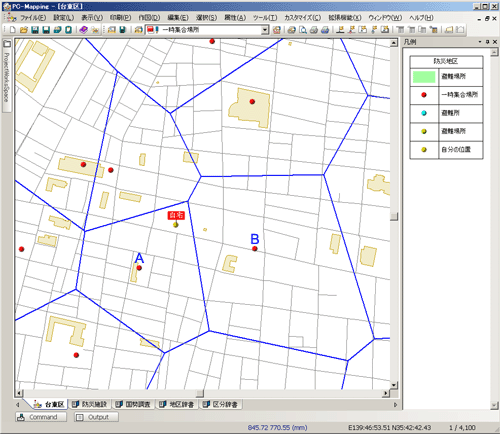
他のネットワーク解析メニューと同様、通行不能のアークやノード、また、アークの方向(一方通行の道路等)を解析のオプションとして指定する事もできます。
「距離の換算」や「選択アークを通過不能とする」オプションの使い方は、 【ネットワーク解析】2点間最短経路をご覧下さい。 【ネットワーク解析】2点間最短経路をご覧下さい。
「ボロノイ分割」については、 【空間統計解析】ボロノイ分割図をご覧下さい。 【空間統計解析】ボロノイ分割図をご覧下さい。
- また、ネットワークのノード(ここでは「道路」レイヤーのノード)には、最寄のポイントの内部IDとそのポイントまでの距離が転記されます。
ノード「C」から近いポイントは「111」で、そのポイントまでの距離は「154.0m」となります。
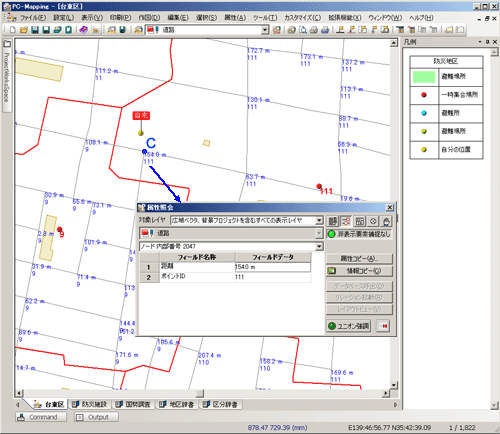
- 領域のポリゴンには、基地ポイントの属性が転記されます。
また、「__PKEY__」というフィールドが新規に生成され、そこには基地ポイントの内部IDが転記されます。
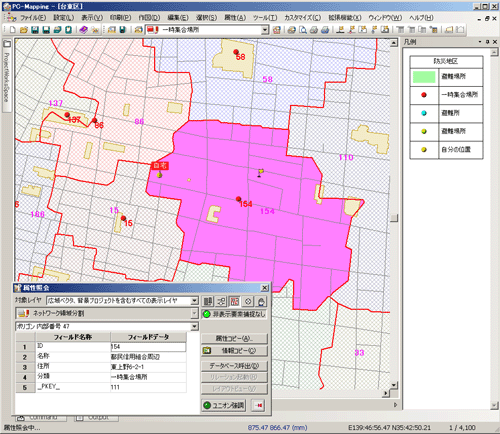
その「__PKEY__」の値を主描画キーとして、自動生成された「ネットワーク領域分割」という名前の描画パラメーターでポリゴンのフィルを塗り潰します。
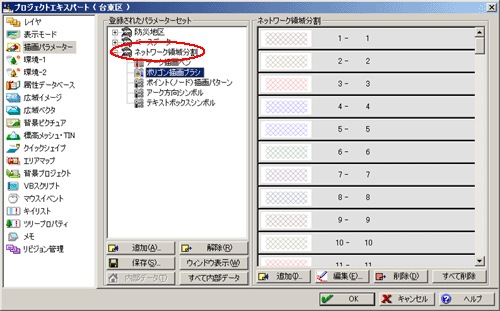
|
















